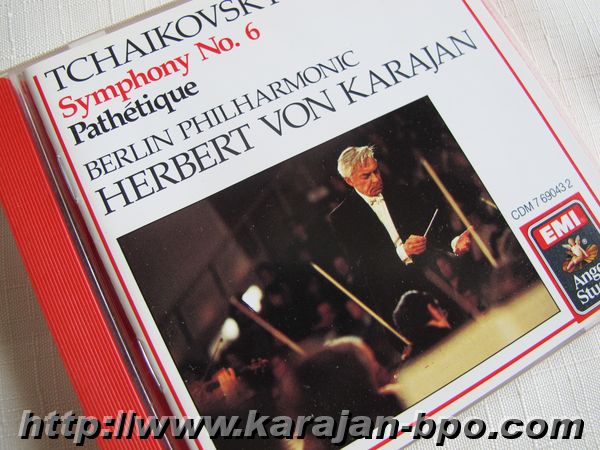甦る1970年の第九—カラヤンとベルリン・フィル、黄金期の記憶
1970年に収録されたカラヤン指揮ベルリン・フィルの《第九》は、長らく“幻”と語られた映像でした。豪華ソリストと合唱団、全盛期のアンサンブルが残した貴重なライブの息づかいを、半世紀を経てあらためて辿ります。
このページの目次
甦る1970年の第九—カラヤンとベルリン・フィル、黄金期の記憶
私が1989年頃に買ったベートーヴェン交響曲全集(グラモフォンのLD)に収録されるはずだった、ユニテル社制作の1970年の第九。ところが、実際にLDに入っていたのは1977年普門館のライブでした。当時の私は「1970年の第九って本当に存在したのだろうか?」と、長いあいだ半分伝説のように感じていたものです。
その後、8ミリや16ミリ、ビデオで海外向けに発売されていたらしいという話は耳にしましたが、実物を見る機会もなく、詳しい情報も入ってきませんでした。それが、思いがけずDVDとして姿を現し、ついに70年の第九と再会できたときの感慨は、今でも忘れられません。
ソプラノのヤノヴィッツ、アルトのルートヴィヒ、バリトンのベリーという「カラヤンお気に入り」の名歌手たちに加えて、クナッパーツブッシュの『パルジファル』やケンペの『ローエングリン』で知られる名ヘルデン・テノール、ジェス・トーマスが加わるという、きわめて豪華な布陣。カラヤンとベルリン・フィルが脂の乗りきった時期に残した、まさに黄金のキャストによる第九と言ってよいでしょう。
1970年という特別な年――来日公演と世界の中の日本
1970年といえば、大阪万博(EXPO’70)の年。世界中の耳と目が日本に集まっていたタイミングで、カラヤン&ベルリン・フィルは日本を訪れ、大阪フェスティバルホールで第九を演奏しました。当時3歳だった私がその場にいられるはずもありませんが、実際にホールで体験された方の話を読むたびに、うらやましさと同時に、あの時代の熱気を少しだけ追体験しているような気持ちになります。
戦後、急速にクラシック音楽を受容していった日本にとって、カラヤンとベルリン・フィルの来日は、単なる一流オーケストラの客演以上の意味を持っていました。「世界最高峰」と目されていたコンビを、リアルタイムでこの目で見ることができる――。そのインパクトの大きさを思うと、1970年の第九の映像・音源が日本のファンにとって特別な価値を持つのは、ある意味当然かもしれません。
フィルハーモニーホールの空気感が伝わるライブ映像
この1970年の第九は、ベルリン・フィルの本拠地フィルハーモニーホールで収録されたライブです。ホール特有の残響、ステージと客席の距離感、オーケストラが立ち上がる瞬間の空気の変化――そういった要素が、スタジオ録音とは少し違った表情を音と映像に刻み込んでいます。
カラヤン&ベルリン・フィルは、1960年代から70年代にかけて何度もベートーヴェンの交響曲を録音してきましたが、ユニテルによる映像作品は、その「音」を視覚化する試みでもありました。指揮台に立つカラヤンの所作、各セクションの受け渡し、管楽器のソロが放たれるタイミングなどを目で追うことで、演奏の構造がより立体的に見えてくるのが、この映像の大きな魅力です。
ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団と豪華ソリストたち
合唱はベルリン・ドイツ・オペラ合唱団。ドイツ語の発音の明瞭さ、声の厚み、フレーズの推進力はさすがで、第4楽章のクライマックスに向けて、じわじわと熱を高めていく様子が実に見事です。オーケストラの分厚い響きに埋もれることなく、「人間の声」が前へ前へと出てくるバランスは、さすがカラヤンならではと言えるでしょう。
ソプラノのヤノヴィッツは、透明感のある響きの中に、どこか抒情的な陰影を含んでいて、歓喜の歌を単なる勝利の歌ではなく、「祈り」にも似た色合いで歌い上げます。ルートヴィヒの深く温かなアルトは、合唱とオーケストラの橋渡し役として絶妙に機能し、ベリーのバリトンは重心の低い安定感で全体を支えます。そしてジェス・トーマスのテノールは、英雄的でありながらも鋭くなりすぎず、ドイツ語のアクセントまではっきりと伝わってくるのが印象的です。
観客ではなく「観客の絵」――不思議な差し替え映像
実際にDVDを見て、思わず苦笑してしまったのが、観客席の映像です。本来ならホールにぎっしりと詰めかけた観客が映っているはずのところに、なぜか板だか紙だかわからない「観客の絵」が据えられているのです。遠目には人が座っているようにも見えますが、よくよく目を凝らすと「これは絵だな」とわかってしまう。
おそらく当時の撮影・放送・権利関係など、今となっては完全には辿れない事情があって、観客をはっきり映せない局面があったのではないかと想像しています。あるいは技術的な都合で客席が十分に撮影できず、後から視覚的な「埋め草」として用意されたのかもしれません。
とはいえ、音そのものは非常に良好で、演奏の集中度も高く、カラヤンのテンポ運びやダイナミクスの付け方は、まさに全盛期のそれ。観客の絵に最初は肩透かしを食らいながらも、いつのまにか音楽の渦に巻き込まれていく――そんな不思議な体験をさせてくれる映像です。もしかすると、この視覚的な違和感こそが、長いあいだお蔵入りになっていた理由の一つだったのかもしれません。
1970年代の黄金期と、他のベートーヴェン録音との位置づけ
カラヤン&ベルリン・フィルにとって、1970年前後はまさに黄金期でした。1960年代のシックで端正な録音から一歩踏み出し、音色に艶と厚みが増し、テンポ感にもゆとりと推進力が同居する成熟の時期に入っています。1963年のスタジオ録音全集、1980年代のデジタル録音全集と聴き比べてみると、1970年の第九はちょうどその中間に位置し、「若々しさ」と「風格」がバランスよく同居していることに気づきます。
同じ曲を、これだけ何度も録音し続けた指揮者はそう多くありません。だからこそ、1970年の第九は、カラヤンの解釈がどのように変化し、ベルリン・フィルのアンサンブルがどのように成長していったのかを知る上で、重要なピースの一つと言えるでしょう。
現代に甦る1970年の第九――いま聴く意味
半世紀以上前のライブ映像でありながら、1970年の第九には、決して色あせない力があります。録音技術や映像クオリティの面では、もちろん最新のブルーレイには及ばない部分もありますが、それを補って余りある「集中」と「熱」がここにはあります。
スタジオでじっくり作り込まれた完成度の高い録音とは別に、ホールという生の空間で、その瞬間にしか生まれない音楽がある。そのことを、カラヤンとベルリン・フィルの全盛期の姿を通して教えてくれるのが、この1970年の第九なのだと思います。若い世代のリスナーにも、ぜひ一度は触れてみてほしい映像です。